2018年の土用の丑の日は7月20日(金)と言われています。
食べると精がつき、暑い夏も乗り切れる、と夏バテ予防のために栄養満点のウナギを、この日に合わせて食べる人もいるのではないでしょうか。
美味しい夏の味覚のウナギですが、ご家族で食べに行ったときに、お子さんが何歳から食べることが出来るのか、気になったことはありませんか。
そもそもウナギを食べてもいい年齢の基準なんて、存在するのでしょうか。
Contents
うなぎは何歳から食べさせることができる?




出典元:https://www.irasutoya.com/
基本的に「○歳から」という定義はありません。
お子さんの歯の成長具合によって変化します。
子どもの乳歯は20本となっており、生後3カ月~9か月ごろに生え始める子がいます。
これは産まれた時に、すでに髪の毛が生えている子もいれば、全然生えてこない子がいるのと同じで、生え始めるタイミングも子どもによって違います。
ですので、まずはご自身のお子さんの歯を確認しましょう。
だいたい最初に生えてくるのが下の前歯です。
その後、上の前歯、それに沿うように横の歯が、犬歯が生えて、奥歯が生えます。
ウナギだけに限らず魚をお子さんに与えるときに、気にしてほしいのが、この「奥歯」の存在です。
ほとんどの子は2歳半ぐらいで、すべての歯が生えそろいます。
ですので、お子さんがウナギを食べれるタイミングは、この「奥歯」が生えたタイミングといえます。
なぜ小さい子供は食べたらだめなの?




出典元:https://www.irasutoya.com/
ではなぜ、「奥歯」が関連してくるかというと、ウナギに限らず、魚には小骨があります。
ウナギや鮎など、骨自体が細く、小さいものであると、お子さんの口に入ってしまったときに、のどに詰まりかねません。
ですので、お子さんが口の中に入れたときに、しっかりと奥歯で噛み砕くことができる、というのがポイントです。
奥歯が生えそろうタイミにングは、お子さんによって違いますが、ウナギの栄養のことを考えてあげたい、というときは、出来るだけ小さくし、骨を必ず取り除いてからあげましょう。
また、ウナギは脂が多い魚です。
もしかしたら消化不良を起こしてしまう場合もありますので、出来る限り少量を与えるようにしてください。
小さい子で食べることができる調理法は?




出典元:https://www.irasutoya.com/
実はウナギには毒があります。
これは小さい子に限らず、哺乳類全般に反応する毒となっており、ウナギの血と粘膜に含まれています。
毒はタンパク質でできており、たくさん摂取してしまうと、死亡してしまうケースもあります。
では、なぜ私たちが普段食べることが出来ているのか。
それは、この毒が熱に弱いからです。
毒は60℃以上で5分以上加熱することで、死滅します。
そのためウナギの料理の「かば焼き」や「白焼き」が主流となっており、私たちが安全に食べることが出来るのです。
ちなみにこの毒は、ウナギだけでなく、ウツボや、アナゴにも含まれておりますので、注意しましょう。
お子さんにあげる際も、十分に加熱されている「かば焼き」や「白焼き」がおすすめです。
毒、と言うと怖いイメージもありますが、ウナギはとても栄養がたっぷり詰まったお魚です。
「土用の丑」といって夏に食べるイメージがありますが、本来の旬は秋から冬にかけて問わえれています。
ですがその栄養価の高さから、夏バテ予防に効くとされ、暑さが本格的になる前に食べるようになったのです。
うなぎは良質なたんぱく質に加え、ビタミンやミネラル、カルシウムなどがたくさん含まれています。
ビタミンには、疲労回復や、細胞の老化予防、成長の促進といった効果があり、食べれば元気が出て、細胞から若返ることが出来ます。
また脂が多く含まれている魚ですが、この脂の中にはDHA(ドコサヘキサエン酸)・EPD(エイコサペンタエン酸)という「賢くなれる」と言われている成分が含まれています。
善玉コレステロールを増やしてくれるこの2つの成分は、生活習慣病の予防にも使われるぐらいで、DHAには脳の発達を助けてくれる成分、EPDにはアレルギーを改善する成分があります。
お子さんの未来を願う、ご家族にとっては、ぴったりの食べ物ですね。
また、ビタミンが多く含まれているウナギでも、ビタミンCの成分は少ないですので、野菜で補うのがいいです。
ビタミンCの含まれている食べ物ですと、ピーマン(特に赤や黄色のもの)・ブロッコリー・カリフラワーなどです。
是非付け合わせとして、ボイルしたものや、おかずとして1品添えると、バランスがよくなるのではないでしょうか。
まとめ
暑くはなくても、なんだかウナギが食べたくなってきましたね。
まだまだ寒暖差があり、5月病という言葉もあるぐらい、春から夏への季節変化は体に負担がかかります。
夏とは言わずに、早めに摂取し、食べるものを変えて体の内側から健康になりましょう。
特に外で仕事をしているご家族がみえる場合、食事が健康の基本ですから、栄養をしっかり考えるのが大切ですね。
「予防」には「早すぎる」ということはありません!

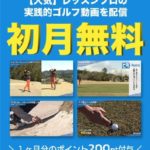






コメント Comments
コメント一覧
コメントはありません。
トラックバックURL
https://trendynewss.xyz/archives/8438/trackback